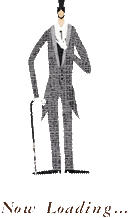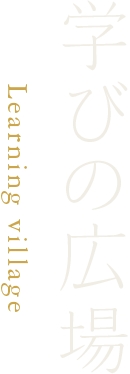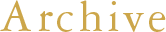Interview 02 望月龍平さん
2017/07/01

望月さんには一度いろいろとお聞きしたかったんですけど、まず劇団四季時代のことをお伺いしてもよろしいですか。
大丈夫ですよ。
劇団四季の舞台は僕も大好きで、「ユタと不思議な仲間たち」をはじめ、他の演目もたくさん見ているんですけれども、その劇団四季では『慣れ、ダレ、崩れ、去れ』という言葉が稽古場に掲げられていると聞いたことがあります。その厳しい稽古の中で龍平さんは『ユタ』ですとか『キャッツ』の『ミストフェリーズ』など、いわゆる主役級の役を獲得するに至っているわけですよね。そこに至るまでの過程や、心境の変化などを教えていただきたいんですが。
まず、劇団四季に入ったときは別にこう、『志』があって…という入り口ではないんですよね。僕の場合は、高校生の時に劇団四季の舞台を見て「あれを自分もやりたい」というのが四季に入ろうと思ったきっかけでした。
それは何だったんですか?
「エクウス」という舞台でした。市村正親さんが初演の時に主役を務められて、先日亡くなってしまいましたが、日下武史さん(劇団四季の創立メンバーの一人)も主役を務められていた、そのお二方の『十八番』と言いますか、伝説的な舞台と言ってもいい、もの凄く面白いお芝居なんですけれども…舞台上で全裸になるんですよ。
ええ!?
僕もその役をやったんです。初めてその舞台を見たのは、加藤敬二さんが演じているときでしたが、あまりにも、見入ってしまったというか。驚くほど簡素な舞台装置で、もう何にもないんですよ。舞台上にリングみたいな空間が用意されているだけ。そこで、精神科医と、ちょっとおかしなことを言う、馬の目を刺した少年が出会って…ていう、そんな設定なんですけどね。とにかくそのお芝居を見て「これをやりたい」というか、「これやる」というか…そんな気持ちになったんですね。
「やるだろうな」と思ったんですか?
思いましたね。だから、入り口としては、やっぱり『個』として自分が、どうしたら俳優としてメインキャストをやれるのか…とか、そういうところでしたね。
劇団四季に入る前は何をされていたんですか?
高校で演劇科に入ったら、そこが当時『四季』と提携を結んでいたので、劇団四季の舞台を見に行くことが多かったんですね。
そうなんですね。で(劇団四季に)入ってからは、稽古稽古の日々になるわけですか?
やっぱり、浅利慶太(劇団四季の創設者の一人)という人はスゴく卓越した経営者であると同時に、卓越したリーダーなんですね。
いつも、同じことばっかり言うんですよ。
とにかく
「慣れるな、ダレるな、崩れるな。崩れたらそのときはもう去るってことになるんだぞ」
とか、
「一音落とすものは去れ」
とか。
それだけじゃなくて、あとはマインドの部分で、
「生きることの感動を伝えるんだ」とか。
そういうことを徹底して舞台で表現しようとしているところに、僕はある意味、「男として惚れた」みたいなところがあったんですよね。だから続けられたんだと思います。
やっぱりときには、理不尽に感じることもあるわけですよ。
だけど、やっぱり彼の伝えようとしていることが解りだすと、
「そうか自分はこのためにやっているんだ」とか、「このために演劇と出会ったんだ」といった発見や気づきが生まれてくるんですね。だから、耐えてこられたというのはありますね。
教育では「個性を伸ばす教育」と言われることがあるんですが、今の浅利さんのお話を伺うと、凡事徹底と言いますか、「一音落とすものは去れ」とか、それこそ、指先の伸ばし方から、足の角度の一つ一つに至るまで、すべてのことを、すべての人に同じようにできることを要求していらっしゃるじゃないですか。それらができるようになったときに、初めて出てくる『役者』による違いこそが『個性』であるということを伝えようとされているように思うんですけど。そういった『個性』が生まれるまで、徹底して練習されるということなんですかね。
まさに、そうなんですよ。
浅利さんは『意識化された個性』というものを嫌う人でしたね。だから、「自分の良さを出そう」と思いながら演技をしているときにはすぐにダメ出しをされるんです。
そして、すぐに
「そのシーンの話の流れはこうで、伝えたいことはこうだ」
ともう一度しっかり意図を説明して、
「そのために俳優は透明でありなさい」
ということを、何度も言われました。
演技の中で、『自分らしさ』を出したいという欲が、別の言い方をすると、自分を良く見せたいという自意識とでも言いますか、浅利さんはそういうものにすごく敏感な方なんですけど、それがちょっとでも見えたときには、もう、激怒…みたいなことが何度もありましたね。
でも、やっぱり全体を見てるんですよね。舞台全体で見ると役者の自分らしさが舞台の良さを邪魔してしまうことになる。
だから、浅利さんの目を信じて、自意識が削がれたところに演技が向かって、役者が透明になったときに
「それでいいんだよ」
って言ってもらえる。
それを頼りに芝居を磨くと、いつの間にか自分の『個性』が育っていくという感覚ですね。
浅利さんの伝えたい「透明とは何か」を僕なりに考えてみると、
「届けたいメッセージを伝えるためには、それぞれが、コマとして、道具として、歯車として、こう動いていったときに本当にいいものが伝わるんだ」
ということじゃないかと感じるようになりました。