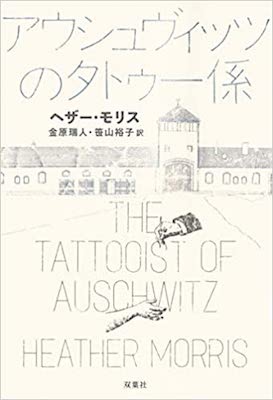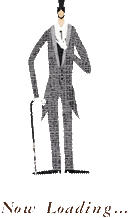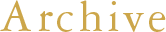アウシュヴィッツのタトゥー係
2022/07/25

Book サロン「Ladybird」で皆さんにプレゼンをしていただいた作品と
ご感想が素敵でしたので、「読書の広場」で紹介させていただいております。
今回はこちらの作品…
📚📚📚
喜多川からの感想
人間の強さというのは、一つのものさしでは測り切れるものではないということを感じるには、アウシュヴィッツや満州からの引き揚げなど、明日の命の保証がない中を、ただ「生きる」ことだけに集中していきた人の人生を知るのが一番だろう。我々が「これだけは譲れない」と思うものをいかに持って生きようとも、「生きる」という唯一の目的のために、過去も築き上げてきたものも、意地もプライドも瞬時に捨て去り、ただ目の前の状況を受け入れ、今できることに集中しようとする、武力なき人々の方が、ナチス親衛隊や狂った医者よりもずっと強い人間だということを教えてもらえた。
ラリはルチカに言った。「君ほど勇敢な人はいない」。
本当に強い人は、暴力を使って相手を服従させようとする残虐性を持った人ではない。生きるためにすべてを耐えると決心したラリやギタ、ルチカ、レオンのような人なのだ。
📚📚📚
ご参加いただいた皆様からのご感想
「生きようとすること」それが英雄的行為だ。
そんな切ない言葉があるだろうか。
これが実話であり、ここまで残酷な世界があったことそのものに戦慄する。
もちろんナチスドイツによるアウシュビッツでの出来事を知らなかったわけではない。
確かにかつてアンネの日記を読んだ記憶もある。だがここまでリアルに恐怖や痛みを感じただろうか。
どこかで自分とは関係のない遠い国の遠い時代の出来事のような気がして、それは「歴史の1ページ」に埋没してしまっていたように思う。
いつも死がすぐそこにある。ユダヤ人であるというだけで。死は突然に訪れる。
主導権を握る側の気まぐれであったり、虫の居所であったり、最悪の場合は残虐な愉しみであったり。
集団殺戮のためのガス室。そこにいつ送られるのかに怯え、飢えた人々が過酷な労働に従事する。
寒さ、恐怖、痛み。働けなくなれば容赦なく殺される。
人間の尊厳を奪われた日々。
狂気に支配された世界は想像するだけで息苦しくなる。
それでも生きようと希望を捨てまいとした人たちの強靭な精神に畏敬の念を抱かずにはいられない。
そんな中にあってラリとギタの間に愛の物語が生まれる。
誰かを愛する気持ちは希望だ。
どんな過酷な状況にあっても人はそういう気持ちを持つことができるのだ。
そして彼らが地獄の日々を生き抜き、愛が成就したことに深い感動を覚える。
彼らを支え、喜びとした人たちがいたことにも。
それにしても人間とは何だろう。運命とは何だろう。
人生には必要なことしか起こらないというが、必然だと言うには惨すぎる人生を、その人は選んでいるとでもいうのだろうか。
ギタの友人であるチルカは上官の慰みものにされ、女性としての尊厳を踏みにじられる。
しかし彼女が誇りを失うことはなかった。
彼女は言った。「生き延びるために。自分がやらなければ誰かがその役をやらなければならなかった」と。
心折れてしまうような日々においてもその信念が彼女を支えていたのだろう。
生きるために心を殺した。組織の中においては加害者側の人間にとっても抗えない運命だったかもしれない。
正当化はできないにしても。
訳者である金子氏は、ラリはアウシュビッツという現実を後世の人々に語るため、その証人として神から遣わされたのではないかと語っている。
過酷な人生を送り、生き延びた人たちは皆そうなのかもしれない。
語り部となって伝え続けていくという使命。
世界各地においては、今この瞬間にも数多の人が不当に弾圧を受けたり、戦禍の中に生きている。
彼らには生命そのものが保証されていない。
そして自分は無力で、彼らのために何もできないことに否応なく気付かされる。
ラリがモットーにしてきた言葉「朝、目が覚めたなら、今日はいい日だ」が心に響く。
私たちの毎日がいかに幸せであるか。3度の食事ができ、暖かい家でゆっくり眠れること。
それだけで十分に幸せであり、不満を言ったらバチがあたりそうだ。
足るを知り、ひとつでもいいから誰かのために何か役立つことをしよう。
朝目覚めることを当たり前だと思える日々に感謝しよう。
「生きている」ことが心から愛おしいと思える。そんなことを深く感じさせられる一冊だった。
📚📚📚
「アウシュヴィッツ」の話に触れた作品を読むのは学生時代ぶりだった。
「本当に人間にこんなことができるのだろうか…」と受け入れられないまま、避けていた部分があったと思う。
ちょうどこの本を紹介していただいた頃、ロシアのウクライナ侵略が始まった。
「昨日までの世界」はこんなにも簡単に壊されてしまうのか。
昨日まで兄弟国と慕っていたその国民をこんなにも簡単に殺せてしまうのか。
言い表せない驚きと失望と深い悲しみ、焦りや危機感が一度にどっと押し寄せた。
アウシュヴィッツのような残虐的な行いは人間のすることではない。
そういう感覚は「グローバル」を掲げていた世界で、
常識になっているだろうと信じて疑わなかった。
毎日毎日流れてくる凄惨な記事やニュースに打ちのめされるばかりだった。
無差別に、そして唐突に
目の前で多くの命が奪われ続けていく。
正気を保つことがどんなにか苦しいか…。
主人公はそんな中で恋をした。
「何としてでも二人で生き抜こう」という覚悟をすることは絶望の中の「光」でもあり、また一方で「生」への執着が強まることで、明日どちらかが殺されてしまうのではないかという心配や苦しみをさらに増幅させるものだったのではないかと思う。
「人は強制収容所に人間をぶちこんですべてを奪うことができるが、たったひとつ、あたえられた環境でいかにふるまうかという、人間としての最後の自由だけは奪えない」
読み進めていく中、「夜と霧」の中のこのフレーズが思い浮かんだ。
なんと強いのだろう。
自分を取り巻く世界は、彼らの世界と比較することが許されないほど満ち足りている。
それを考えると、「まだできる」「まだいける」と思えることが溢れてくる。
今ある環境がいかに幸せか、「ある」ことが「難しい」環境なのかということ、
そして、この幸せは「覚悟」を持って守っていかないといけないものなのだということを感じさせられた。